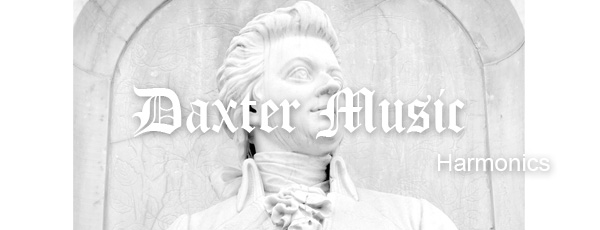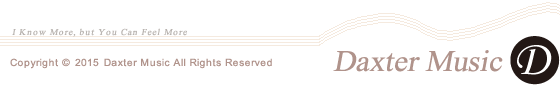古典派時代の演奏会におけるプログラムは、まさにその時代の「現代音楽」で、シンフォニーの切り貼りのようなプログラムも多かったそうです。入場料は1グルデン(現代円で5,000~10,000円)。交響曲38番の大成功に気を良くしたモーツァルトが、「フィガロの結婚」の変奏曲を即興演奏してくれたこともあったそうです。
ヒュッファーという人物は、仕事仲間に連れられモーツァルト未亡人コンスタンツェと一夕を共にした際のことを次のように回想をしています。
彼女は亡き夫モーツァルトについて、大変面白い話をしてくれた。たとえば、モーツァルトは全く明りを取り払った部屋で眠り、正午までは起きてこない。昼食が済むと仕事を始めるのだが、彼女(未亡人コンスタンツェ)にいわせると、その時はただ(楽譜の)コピーを取っているだけで、作曲はすでに午前中に行われているということである。
交響曲39番から41番までをわずか2か月前後で作曲したという超人的な能力のある彼ですが、晩年の(仕事人としての)活動時間帯は主に午前中だったようです。たしかに、仕事が逼迫すればするほど、寝起き数時間(2,3時間)というのは、余計な思考が働かずに集中力が持続する時間帯のような気もします。あるいは暗いベッドの中で何らかのインスピレーションを得ていたのかもしれません。彼にとって、午後という時間帯は単なる充電の時間だったのかもしれませんが、天才が努力を重ねった結果、手にしたルーティンと言えるのでしょうか。
時代と音楽の本質
華々しい世界的なコンサートに臨む指揮者や演奏家の心境はどのようなものでしょうか。 2022年の元旦にウィーンフィルを指揮したダニエル・バレンボイムは「(シュトラウスのマーチやワルツなど)音楽には自由が求められますが、やりすぎでも不足していても、魅力を損ないます。皆さんは(ウィーンフィルの)団員はスタイルを知っていて楽に構えていると思うかもしれませんが、実際はそんなことはありません。リハーサル中はとても集中しています。」と語っていましたが、現代を代表する指揮者として、音楽の本質部分と演奏時の緊張感を同時に伝えてくれています。
ともするとニューイヤーコンサートなどは華やかな部分が先行しているかもしれませんが、ウィーンフィルのチェアマンであるダニエル・フロシャウアーも19世紀の音楽について「すべての作品に小宇宙がある」と評しているように、高い緊張感をもって臨んでいることが窺えます。どの方も向き合う姿勢が真摯です。
また、楽聖ベートーベンはドイツの女流作家ベッティーナ・フォン・アルニムに対し、
音楽は精神生活を感覚的に表現するのによい方法である。旋律はポエジーの感覚的な生命であって、旋律につつまれた精神は、無碍の普遍性をもって拡がり、単純な音楽的思想から生まれてそれがなくては消えてしまうような感情の温床を万人の中につくりだす。この温床が和音であって、自分のシンフォニーはこれを表現し、その中では様々な形式を融合したものが、母床から先端に至るまで波動している。人はそこに永遠にして無限なる、決してことごとくは抱括し得ぬものを感じるだろう。
私のシンフォニーをきけば、ゲーテは音楽が高い叡智の世界への唯一つの非肉体的な入口であり、人間はそれに包まれているのだが、自分ではそのことを知らずにいるという、私の言葉の正しいことを認めるだろう。精神が、感性的に音楽から感じるものは、知識の形象化されたものである。音楽の究めつくせない法則に服従すれば、この法則は精神を制約し、支配し、啓示を行ってくれる。
と語っています。
それらしい文章を読むとすぐに興奮し、誤解する人も出てきますが、ベートーベンの評価するものは、素直で、まっすぐで、密度のある和音だと思います。ベートーベン自身はこれらの発言を「そんなこと言ったの?じゃきっとラプトゥス(熱狂:境に入る)していたんだ」と少々照れながら?振り返ったそうですが、クラシックの良さはやはりその「中身(本質部分)」です。
その素晴らしさをよく知っている皆さまとこのサイトも盛り上げていきたいなと考えております。
人気コンテンツ daxter-music.jp